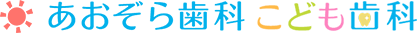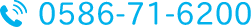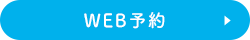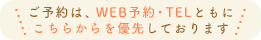こどもの歯並びが気になっている保護者の方は多いのではないでしょうか。
歯並びの乱れは、見た目の問題だけでなく、咀嚼や発音、姿勢や集中力など、さまざまな面に影響する可能性があります。
歯並びは遺伝と思われがちですが、生活習慣や癖によっても大きく左右されます。
この記事では、こどもが悪い歯並びになる原因として特に注意したい5つの癖・習慣を紹介し、それぞれがどのような歯並びの乱れにつながるのかについて詳しく解説します。
目次
■こどもの歯並びが悪くなる原因
◎指しゃぶりが長く続く
指しゃぶりは乳児期によく見られる行動で、成長の過程で自然にやめていくことが多いですが、3歳を過ぎても続いている場合は注意が必要です。
また、指が歯に常に当たっていることで歯並びだけでなく、上顎の骨の成長に影響するケースも見られます。
◎口呼吸の習慣がある
本来、呼吸は鼻で行うのが正常ですが、鼻づまりやアレルギーなどによって口で呼吸する癖がついてしまうことがあります。
口呼吸が習慣化すると、口の周りの筋肉が弱くなり、歯列を正しく支えられなくなります。
その結果、歯が前に出やすくなったり、上下の噛み合わせがずれたりする原因となり、開咬(かいこう)や出っ歯、受け口のような歯並びになることがあります。
◎頬杖をつく癖がある
勉強中やテレビを見ているときなど、無意識に頬杖をついてしまうこどもは少なくありません。
しかし、いつも同じ方向に頬杖をついていると、顎の骨の成長に偏りが生じ、顎がゆがんだり、歯列全体が片側に寄ってしまったりする可能性があります。
◎片側だけで噛む習慣がある
食事のときに片側ばかりで噛む癖があると、顎の成長が左右でアンバランスになり、歯並びや噛み合わせが偏りやすくなります。
このような噛み方を長く続けていると、顔の筋肉や骨格にも影響が出て、左右非対称な顔立ちになってしまう子もいます。
◎舌の使い方に癖がある
舌を正しい位置に置く習慣がないと、歯並びに影響が出ることがあります。
例えば、食べ物を飲み込むときに舌で前歯を押す癖があると、前歯が押し出されて、開咬や出っ歯になる原因となります。
また、舌が下の方に位置していると、上顎の骨の発育が妨げられ、歯列が狭くなってしまい、歯がきれいに並ぶスペースが不足し、歯並びが乱れてしまうこともあります。
■こどもの歯並びを守るためにできること
◎生活習慣を見直す
日頃の姿勢や食べ方、呼吸の仕方を見直すだけでも、歯並びへの影響を軽くできることがあります。
指しゃぶりや頬杖、片側噛みなど、気になる癖がある場合は、無理にやめさせようとするのではなく、やさしく声かけをしながら少しずつ改善を促しましょう。
◎食事内容を見直す
柔らかい食べ物ばかりを食べていると、顎の発達が不十分になり、歯が並ぶスペースが不足することがあります。
加工食品のような柔らかいものだけでなく、よく噛む必要のある食材を取り入れ、噛む力を育てることで、口腔周辺の健全な筋肉や骨を育てることができます。
◎歯科医院に相談する
こどもの歯並びに不安がある場合や、癖をやめられない場合は、小児歯科や矯正歯科での相談をおすすめします。
定期検診を受けることで、歯並びの問題を早く発見し、必要に応じた治療を受けることができます。
【こどもの頃からきれいな歯並び習慣を】
こどもの歯並びは、遺伝だけでなく日常の癖や生活習慣によっても大きく左右されます。
指しゃぶりや口呼吸、頬杖など、些細な行動が将来的な歯並びの乱れにつながることもあるため、日頃の様子をしっかり観察してあげることが大切です。
悪い歯並びは見た目だけでなく、噛み合わせや健康にも影響するため、気になる癖がある場合は早めに歯科医院に相談しましょう。