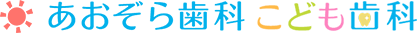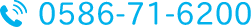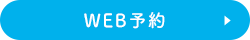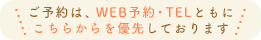こどもの歯並びが気になっていても「そのうち生え変わるから大丈夫」と様子を見る方は少なくありません。
しかし、歯並びの乱れをそのまま放置していると、見た目だけでなく、体の機能や健康に影響する可能性があります。
特に、成長期のこどもの場合は、顎の発達や生活習慣に大きな影響が出るため、注意が必要です。
この記事では、悪い歯並びをそのままにすることで起こりうるリスクや、その対策について詳しく解説します。
目次
■悪い歯並びが引き起こす問題とは?
◎見た目のコンプレックスになることがある
歯並びは、顔の印象を大きく左右する要素です。
前歯が重なっていたり、前に出ていたりすると、口を開けて笑うことに抵抗を感じるようになる子もいます。
こうした見た目のコンプレックスは、思春期以降に強く表れやすく、自己肯定感の低下や人前で話すことへの苦手意識につながることがあります。
◎咀嚼や発音に支障が出る
歯並びが悪いと、上下の歯がうまくかみ合わず、食べ物をしっかり噛めなくなる場合があります。
よく噛めないことで消化が悪くなり、胃腸に負担がかかることもあるほか、顎の成長が偏ってしまう原因にもなります。
また、「サ行」や「タ行」などの発音が不明瞭になることもあり、コミュニケーションの苦手意識が強くなるケースもあります。
◎むし歯や歯周病になりやすくなる
歯並びが悪いと、うまく歯ブラシが届かず歯と歯の間に汚れが溜まりやすくなります。毎日の歯みがきでは取りきれない場所が増えてしまい、歯垢(プラーク)や歯石が付着しやすく、むし歯や歯周病のリスクが高くなります。
乳歯期からこのような状態が続くと、永久歯が生えてきたあともトラブルが多くなる傾向にあります。
◎姿勢や呼吸に影響することも
実は、歯並びの乱れと姿勢や呼吸には密接な関係があります。
例えば、出っ歯や開咬(奥歯を噛み合わせた時に上下の前歯に隙間ができて噛み合わない)などの症状があると、口呼吸になりやすく、舌の位置も下がってしまうことがあります。
口が開いたままになることで顔の筋肉のバランスが崩れ、猫背などの姿勢不良につながることもあります。
姿勢の乱れは全身の筋肉や集中力にも影響するため、成長期のこどもにとって無視できない要素です。
■放置によって矯正が難しくなるケースも
◎骨格のバランスが崩れると治療が複雑に
歯並びの問題が長期間放置されると、単なる歯のズレにとどまらず、骨格そのものに影響することがあります。
顎の骨が左右でバランスよく成長しない・上下で位置がズレてしまうと、矯正治療の際に歯を動かすスペースが足りなかったり、外科的な処置が必要になったりすることもあります。
早期に治療を始めることで、歯や顎の成長に合わせた矯正が可能になります。
◎成長が終わってからでは選択肢が限られる
こどものうちは、顎の骨がやわらかく柔軟に動かせるため、歯列や噛み合わせを整えやすいというメリットがあります。
しかし、顎の骨の成長が終わった大人になってから矯正を始めると、歯を適切に並べるスペースが足りずに抜歯する必要があったり、治療に長い期間がかかったりする場合もあります。
歯並びの改善を望む場合は、早めの相談が良いでしょう。
■こんな様子が見られたら注意が必要
こどもの歯並びに問題があるかどうかを判断するのは難しいこともありますが、以下のような様子が見られる場合には注意が必要です。
-
口を閉じていても前歯が出ている
-
口呼吸をしていることが多い
-
上下の前歯が噛み合っていない
-
食べ物を片側ばかりで噛んでいる
-
発音がはっきりしないことが多い
これらの兆候がある場合には、まず歯科医院で相談してみることで必要な治療を提案してもらえるでしょう。
【歯並びの乱れは放置せず、早めの対応を】
歯並びの乱れは、見た目だけでなく、咀嚼、発音、姿勢、呼吸、さらには将来の矯正治療の難易度にも関わります。
特にこどもの場合は、成長過程で適切に対処することで、多くのトラブルを防ぐことができます。
そのうち治るだろうと見過ごさず、気になる様子があれば早めに歯科医院に相談してみましょう。